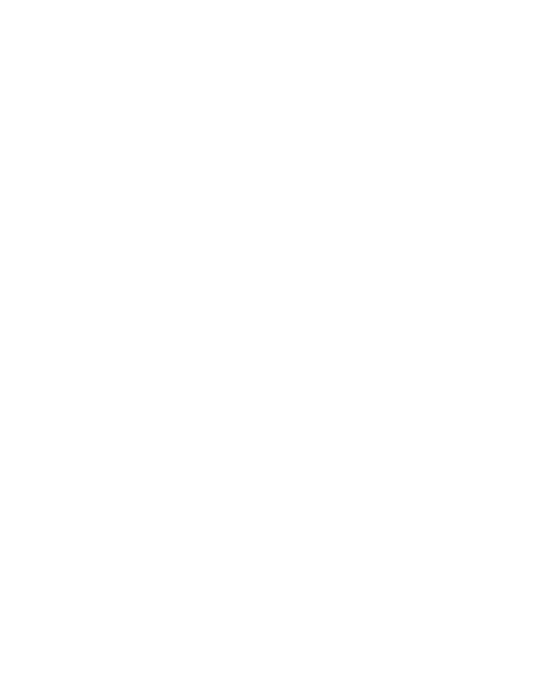オッペンハイマー | Oppenheimer (2023)
- Shoji Taniguchi

- Dec 29, 2024
- 3 min read
4.3/5.0
「原爆の父」ロバート・オッペンハイマーの半生を描いた伝記映画で、「ダークナイト」「インターステラー」「テネット」を手掛けたクリストファー・ノーランが脚本・監督・製作を担っている。
主人公のオッペンハイマーを演じるのは、ノーラン監督作品の常連ともいえる名優キリアン・マーフィー。
エミリー・ブラント、マット・デイモン、フローレンス・ピュー、ロバート・ダウニー・Jrといった超一流俳優達が助演しており、その迫真の演技に圧倒され、まるでドキュメンタリー映画を観ているような錯覚に陥るほど。
第二次世界大戦当時、米国の敵対国だった日本の広島と長崎に投下された2発の原子爆弾がどんな人々によってどのような経緯で開発されていったのか、またその開発の成功が (原子爆弾の直接被害を受けた日本人達のみならず) 開発者やその関係者達にどんな結末をもたらしたのかについて、どの登場人物とも精神的な距離が置かれながら描かれる。
広島と長崎の壊滅を正当な行為だったと認めることは日本人として絶対にできないが、作中でも触れられる通り、仮にオッペンハイマーやその同僚たちが原子爆弾の開発に失敗した世界があったとしても、他の誰かがおそらく同様の破壊兵器を生み出すことになったのだろう。
純粋な動機に基づく科学的探求の末、こういった現象が存在すると突き止め、それを自らの手で実証できそうだと分かった時、人類はまだ、それを目にしてみたいという欲求を自制できない未熟な生物なのだ。
日本人としてもっとも心が痛んだシーンは、完成した原子爆弾を日本のどの都市に投下するかについて米国人達が議論するシーンだった。
広島と長崎だけでなく、京都・新潟・小倉といった都市もその候補に入っていたこと、もしかしたらそれらの都市が壊滅していたかも知れないことと、その決定の過程があまりにも軽薄だったことに、戦争という行為への憤りを感じずにいられなかった。
オッペンハイマーが終劇間際に幻視する、核を搭載したロケットが世界中で発射され地球が燃え上がるシーンは、神から火を盗み人間に与えたプロメテウスのように、人類がまだ触れてはいけなかった核という火を世界に与えてしまったオッペンハイマーの後悔と恐怖が見事に表現されていた。
私たちは、オッペンハイマーが切り開いてしまった、核兵器が大量に存在する破滅間際の世界に生きている。
そして、その破滅がいつ、どんなきっかけで、誰が住む街から始まるのか、誰にも予測できないのだ。
ノーラン監督が手掛けてきたSF系映画やコミック原作映画とは全くジャンルが違う伝記ものかつものすごく重いテーマということがあって、なかなか鑑賞する気持ちになれず、鑑賞後にもやはりとても重い読後感が残ったが、この作品を観ることができて良かったと感じた。